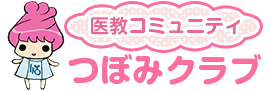この「国試対策勉強法」では、みなさんが国試合格を目指して勉強していくときに役立つポイントをご紹介していきます。
今年度の連載は、以下の順番で解説していく予定です。
1.疾病の基礎
2.成人看護(疾患別ポイント)
3.必修完全攻略
4.老年・小児看護
5.母性・精神看護
6.在宅・社会福祉・統合問題
今回はイントロダクションとして、看護師国家試験における解剖生理の重要性をお伝えしたいと思います。
1.出題基準はどれだけ広い?
看護師国家試験の勉強を始めるにあたり、まず最初に知ってほしいのは「出題基準の膨大さ」です。
看護師国家試験 出題基準(令和5年版)
厚生労働省が定める出題基準は、大項目・中項目・小項目に細かく分かれており、必修問題だけでも小項目が243個も設定されています。国試に合格するためには、これらひとつひとつを理解し、説明できるようになることが必要です。しかし、すべてを一度に覚えるのは現実的ではなく、「どこから」「どの順番で」学ぶかが、合格のカギになります。
そして、国家試験の出題範囲は、「人体の構造と機能(解剖生理)」から「疾病の成り立ちと回復の促進(疾患)」「各看護領域」まで、多岐にわたります。しかも、各分野ごとに細かい知識や判断力が求められ、単なる暗記だけでは対応できません。この膨大な範囲を前に、どこから手をつければよいか迷う人も多いはずです。
2.どこから勉強すればいい? その順番が合格への近道!
結論から言うと、まず「解剖生理(人体の構造と機能)」から始めるのが最も効率的です。
その理由は……
1)すべての基礎は「解剖」から
解剖生理は、人体の「地図」と「しくみ」を知る学問です。
病気の理解も、看護ケアの根拠も、すべては「体がどうできているか・どう働いているか」を知っていないと始まりません。
2)疾患や看護の学びも「解剖」が土台
例えば、心臓の病気を学ぶとき、心臓の構造や血液の流れがわからなければ、症状や治療が理解できません。
また、患者さんへのケアや観察も「どの臓器がどうなっているか」を知らないと、適切な判断ができません。
3)効率よく知識を積み上げられる
まず解剖生理を押さえ、その上に疾患の知識、さらに看護技術やケアの知識を重ねていくことで、全体像がつながりやすくなるのです。
つまり、解剖生理がわかっていなければ、病気も看護も本質的には理解できない、ということなのです。
国家試験の問題は、単なる知識の暗記だけでなく、「なぜこの症状が出るのか」「なぜこのケアが必要なのか」を根拠をもって答える力が求められます。その根拠となるのが、まさに「解剖生理」の知識です。
この土台がしっかりしていなければ、どれだけ疾患や看護の知識を積み重ねても、応用力や本質的な理解にはつながりません。

3.効率的な学習の流れは?
ズバリ!
2.疾患(疾病の成り立ちと回復の促進)
3.看護(各領域の看護・ケア)
この順番で学ぶことで、知識が「点」ではなく「線」や「面」としてつながり、国家試験だけでなく、実際の看護現場でも役立つ力が身につきます。
出題基準の膨大さに圧倒されるかもしれませんが、「解剖」から着実に学ぶことが、合格への最短ルートです。
まずは人体の「地図」と「しくみ」をしっかり理解し、その上に疾患や看護の知識を積み重ねていきましょう。
この順番こそが、国家試験を攻略するための最も確実な方法です。
次回から、解説動画を交えて、各ポイントを説明してきますよ。
ぜひご覧ください!